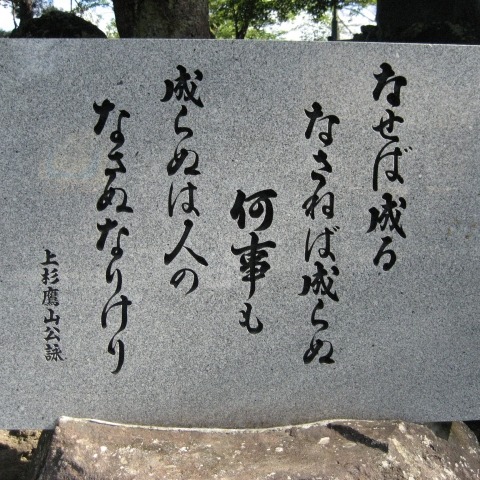最近、買い物に行くたびに値上がりしていることを感じていませんか?食料品や日用品、ガソリン代までもが、知らぬ間に価格が上がってしまい、家計を管理するうえで不安に思われる方も多いのではないでしょうか。毎日の生活の中で、少しずつ積み重なっていく値上げに、どう対応すれば良いのか迷うこともあるかもしれません。こうした「値上がり」は、経済の現象である「インフレーション」に関連しています。

インフレーションとは?
インフレーションとは一体何なのでしょうか?簡単に言うと、インフレーションとは、商品やサービスの価格が全体的に上昇することを指します。これは一時的なものではなく、持続的な現象として社会全体に影響を及ぼします。そしてこのインフレーションには、主に2つの要因が挙げられます。それがコストプッシュインフレーションとディマンドプルインフレーションです。今回の記事では、コストプッシュインフレーションについて解説していきます。
コストプッシュインフレーションの要因とは?

コストプッシュインフレーションの事例
直近の事例として、2022年から続く原油価格の高騰が挙げられます。この原油価格の上昇は、ガソリンや電気代などエネルギー関連の価格に直接影響を与えました。さらに、物流コストの上昇や、原材料の輸入にかかる費用の増加が加わり、食品や日用品の価格にも波及しました。私たちの生活に原油製品は欠かすことができません。ひとつずつの家計に現れた影響が広がり、日本国内の消費者に影響を与え、日常生活における幅広い商品で値上がりが発生しました。
2022年から2023年にかけての国内消費者物価指数(CPI)のデータを見ても、特にエネルギー価格が大きく上昇しており、それが他の分野にも波及していることが確認されています。このデータは、実際にコストプッシュインフレーションが日本の経済に影響を与えていることを示しています。
日本経済の変化
このコストプッシュインフレーションにより、日本経済は消費者の購買力が低下し、家計の負担が増加しました。特にエネルギー価格の高騰により、多くの家庭が電気代やガス代に苦しんでいます。また、企業側でもコストの増加に伴い、価格転嫁を行わざるを得なくなり、結果的に商品価格の上昇が連鎖的に続いています。この影響で、消費が抑えられ、経済成長が鈍化する懸念が高まっています。
今後の日本経済の動き
これらを踏まえると、今後もコストプッシュインフレーションが日本経済に大きな影響を与え続ける可能性があります。特に、エネルギーや原材料の供給問題が長期化する場合、価格の上昇は今後も続くでしょう。しかし、技術革新や代替エネルギーの普及など、コストの抑制に向けた取り組みが進むことで、徐々に価格の安定が期待されます。
消費者としては、これらの動きを見極めつつ、節約や効率的な家計管理を行い、家計を守るための工夫が求められる時代が続きそうです。
金融リテラシーの向上が鍵
インフレ時代を生き抜くために、家計管理の見直しや柔軟な適応力が大切なのはもちろんですが、最も重要なのは 金融リテラシーの向上 です。インフレによってお金の価値が変わる中、自分の資産をどう守り、どう増やすかを理解しておくことがこれからの時代には欠かせません。
金融リテラシーを高めることで、インフレに対する備えだけでなく、適切な投資や貯蓄を行い、長期的に家計を豊かにすることが可能です。これからも、経済の動きをしっかりと理解し、家族や自身の未来のために、正しいお金の知識を身に付けていきましょう。それが、安定した生活を守り、インフレの影響を最小限に抑えるための最善策です。
株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄
『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
この記事の続編の記事はこちら
値上がりに困っているお母さまへ-家計を守るために今知っておきたいインフレの仕組み