「金融リテラシーとは何か?」と問われると、多くの人がその重要性を理解しているものの、具体的な内容についてはまだまだ理解が進んでいないのが現状です。「金融リテラシーとは」記事でも述べたように、日本の金融リテラシーは他の先進諸国と比べて低い水準にあります。さらに、学校教育での金融教育カリキュラムも十分に整備されておらず、これが日本における金融リテラシーの向上を妨げる一因となっています。
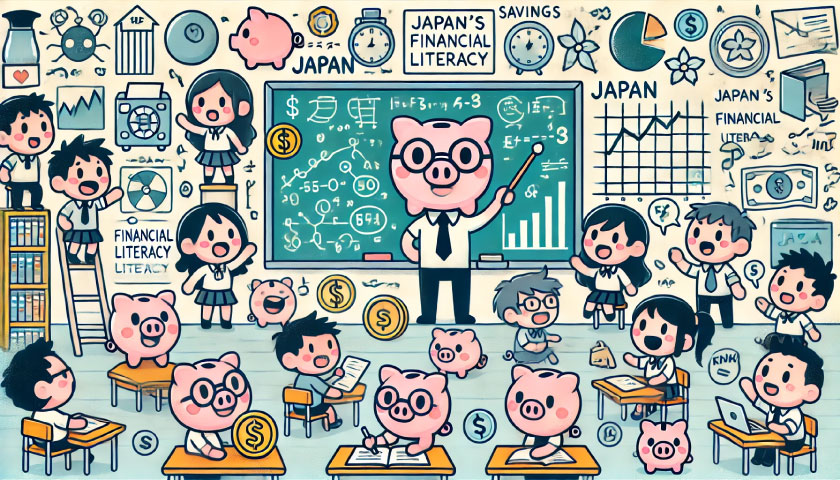
このブログでは、日本の金融リテラシーの現状をより具体的に理解するために、さまざまな調査結果とデータを基に、その課題と改善の方向性について考察します。これらのデータを参照することで、金融リテラシーを高めることがなぜ重要であり、どのような方法で実現できるかを具体的に探っていきます。
↓元記事はこちらから↓
1. 日本の金融リテラシーが低いことを示すデータ
OECDの調査結果
- 経済協力開発機構(OECD)は、金融リテラシーに関する国際比較調査を定期的に実施しています。2020年の「OECD/INFE国際金融リテラシー調査」によると、日本の成人の金融リテラシースコアは平均よりも低く、特に「貯蓄や投資に関する知識」「リスクとリターンの理解」などの項目で他国と比べて劣っていることが明らかになっています。
日本銀行の調査
- 日本銀行が行った「家計の金融行動に関する世論調査」(2021年)によれば、日本の世帯のうち約60%が「貯蓄をしているが、投資にはあまり関心がない」と回答しています。これは、投資教育の不足やリスク回避の傾向が強いことを反映しており、金融リテラシーの低さの一因となっています。
2. 学校教育における金融リテラシーの不足
文部科学省のカリキュラム分析
- 文部科学省が発行する「学習指導要領」では、経済や金融に関する内容は社会科(中学、高校)で一部触れられるのみです。具体的な投資、ローン、リスク管理などの金融リテラシーを育成するための科目は現在設けられていないため、専門的な知識やスキルの習得には至っていないことが指摘されています。
NPO法人フィナンシャル・ジェネラル教育推進会の調査
- NPO法人フィナンシャル・ジェネラル教育推進会が2022年に実施した調査によると、日本の高校生の70%以上が「お金の管理方法や投資について学校で学んだことがない」と回答しています。この調査結果は、金融リテラシー教育が学校で十分に行われていないことを示しています。
3. 金融リテラシーを身に付けたいと考えている人の多さ
日本証券業協会の調査
- 日本証券業協会が行った「個人投資家に関する意識調査」(2022年)によると、20代から40代の若年層の約80%が「投資やお金の運用に興味があるが、具体的な知識が足りない」と回答しています。これにより、金融リテラシーを学びたいと考えている人が多いことが裏付けられます。
まとめ
「日本の金融リテラシーの現状:データと調査結果から見る課題」では、日本における金融リテラシーの水準が他の先進国と比較して低いこと、そして学校教育における金融教育の不足がその一因となっていることをデータと調査結果をもとに明らかにしました。日本の金融リテラシーを向上させるためには、個人の自主的な学びとともに、教育システムの改善が求められます。
金融リテラシーを高めることは、個人だけでなく社会全体の経済的な安定と成長に繋がります。私たち一人ひとりが金融リテラシーの重要性を理解し、積極的に学ぶ姿勢を持つことが、より豊かな未来を築くための鍵となるでしょう。






